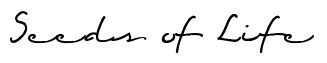米国の株式市場はバブルではありませんが、一部で「火災」が発生しているようです。
年初以来のの上昇率を見ると、大手テクノロジー株で構成する「NYSE FANG+指数」は78%、最近公開された銘柄を保有する上場投資信託(ETF)「ルネサンスIPO ETF」が84%、再生可能エネルギー企業に投資する「SPDR S&P ケンショー・クリーンパワーETF」は88%にも上ります。
この間、市場全体は約11%上昇したのみでした。
これは非常に重要な違いであると言えるでしょう。
金融資産が過大評価された状態を「バブル」と呼ぶのは今に始まったことではありません。
市場価格を限界まで膨張させる大規模な投機を指す金融用語としての「バブル」の起源は数世紀前にまで遡ることができます。
しかし金融バブルはこれまで正式に定義されたことはなく、あとで振り返ってみて「ああ、あの時がそうだった」と気付く以外、見極めるのは非常に難しいものです。
北アイルランドのクイーンズ大学ベルファストで金融論を教えるウィリアム・クイン、ジョン・ターナー両氏による新刊本「Boom and Bust: A Global History of Financial Bubbles(ブームとバースト:金融バブルの世界史)」はこのテーマについて混乱した思考の整理に役立つことでしょう。
バブルのイメージは実際のバブルとはかけ離れています。
ガムをかんだことがある子どもなら誰でも知っているように、バブルはそこそこ膨らんだだけで破裂することが多いものです。
親や教師以外の人にとっては、それほど気になるものでもありません。
しかし金融市場は簡単に5倍や10倍にまで膨れ上がり、一瞬で少なくとも50%は下落して、何百万人もの投機家にやけどを負わせ、一国の経済を黒焦げにすることさえあります。
1929年の株価大暴落後の米国や、それから約60年後の日本を考えてみればいいでしょう。
過大評価された資産はバブルととらえるより、火災と考えたほうがいいのかもしれません。
火災は燃え広がれば広がるほど、そして熱くなればなるほど、大きな惨事を招きます。
「Boom and Bust」では『火の三角形』の例えを使って、過去300年に起きた市場の熱狂を丹念に検証しています。
火の三角形のイメージは火がついて燃え続けるために必要な条件である酸素、燃料、熱を説明するために使われています。
三つのうち一つを取り除けば、火災を防いだり火を消したりすることができるという訳です。
投資における『酸素』とは市場性、つまり資産の売り買いのしやすさを表しています。
数世紀前なら譲渡しにくい企業の所有権を売買可能な株式に分割することであり、今の時代ならポケットに株式仲買人を入れて持ち歩くことだって可能です。
スマートフォンのアプリを使えば、誰でも買える単位でいわゆる「端株」を売買できます。
ロビンフッドのような人気取引アプリでは、1株約34万5000ドルのバークシャー・ハザウェイのクラスA株に1ドルを投資して、約0.000003株の持ち分を手数料なしで取引することができます。
火の三角形の二つ目の辺である『燃料』は、金融市場では資金や信用という形で表されます。
低金利の借入資金での投資が安価に行えるようになる一方で、安全貯蓄の利回りは減り、人々はよりリスクの高い資産に投資せざるを得ない状況にあります。
今は、巨大な資産を運用するプライベートエクイティ会社が企業を丸ごと買収したりするかと思えば、個人投資家が株式売買口座にある2000ドルを元手にして小口の信用取引をしたりする有様を、借入資金が後押ししています。
三角形の三つ目の辺である『熱』を提供するのは投機です。
価格が上がると、より多くの人が買いに走り、価格はさらに上がって、投機家がまた殺到するわけです。
こうした状況が、利益は簡単に上げられると思っている世間知らずの買い手を魅了します。
しかしヘッジファンドなどの機関投資家も高い利回りを追いかけ、炎はますます高く燃え上がっていきます。
「Boom and Bust」によれば、火の三角形は近年改訂されて『発熱を伴う連鎖反応』という第4の要素が加わわりました。
市場性・信用・投機は市場で火を起こして燃やし続けるのには欠かせませんが、それだけで足りないという指摘です。
著者らが「火花」と呼ぶ第4の要素に着目するべきです。
この「火花」をもたらすことができるのは、新たなテクノロジー、または政府の介入、あるいはその両方です。
1990年代後半の株式投資ブームはインターネットの可能性をめぐる楽観ムードが引き起こしました。
中国で近年起きた投資ブームをあおったのは政府の政策とプロパガンダです。
「Boom and Bust」によれば、ほとんどのバブルはごく一部の銘柄や業界に限定される傾向にあると指摘されています。
1824~25年がそうでした。
当時、ロンドンで上場していた中南米の鉱山株は約半年で5倍以上値上がりしましたが、この間、英国の優良企業は時価総額のほぼ10分の1を失いました。
1890年代には同じロンドンで自転車企業の株価が1年で2倍以上になりましたが、主要銘柄に動きはありませんでした。
インターネット株が急騰した1999年には、テクノロジー株の比重が大きいナスダック総合指数が86%上昇したものの、テクノロジー株を除外すれば、S&P500種株価指数の上昇率は5%にとどまっていました。
今の状況は当時とそう変わりはありません。
投資会社マタリン・キャピタル・マネジメントによると、S&P500種指数の今後12カ月の予想株価収益率(PER)はこのところ21倍で推移しています。
これは過去四半世紀の平均を約24%も上回っています。
筆者が見るところ、新規上場銘柄や代替エネルギー企業、買収のために設立されたシェル企業(ダミー会社)のような比較的狭い領域での過熱については、懸念材料はそれほど多くはありません。
それより心配なのは、一部の超大型株の間で起きている火災が周辺に延焼することです。
2000年にはテクノロジー株の比重が大きいナスダック総合指数が暴落すると、より広い業種で構成されるS&P500種種数も大きく下落しました。
このところ、小型株や割安な「バリュー」株が回復の兆しを見せ始めていいます。
もしこの傾向が続けば、アマゾンのように高騰する超大型株の市場でのウエートが下がる可能性があります。
これこそ今の市場が必要としている『防火帯』なのかもしれません。
ジェイソン・ツヴァイク(WSJのパーソナル・ファイナンス担当コラムニスト)のコラムより
The Wall Street Journal