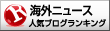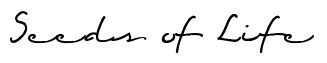ショーンに会いたい、無性に会いたい。
新型コロナウイルスの感染拡大が起きる前、彼の仕事場は廊下の先にありました。
筆者と同じく自宅よりオフィスで働くのが好きで、筆者と同じくポストパンクの音楽を聴き、政治を巡って気の利いたジョークを言い、午後にはエスプレッソを楽しみました。
10分以上会話が続くことはめったにありませんでしたが、ショーンは12年間のほぼ毎日、私の働く日常における社会的構造の一部となっていました。
この1年間、われわれはテキストメッセージを数回、メールを数回交換しました。
ですが、以前ほど深い繋がりは感じません。
企業はオフィスを再開し、恐らく従業員に戻るかどうかの選択肢を与えるでしょう。
企業も従業員も考慮すべきことは、物理的空間を共有しなければ、自分自身でさえ、ほとんど気づかない(それを表現する適切な言葉が見つかりません)人間関係を失うであろうということです。
とりたてて友人でもない、こうした知り合いと、われわれはおしゃべりしたり、出勤時に顔を合わせたりします。
それを表面的関係と片付けるのは簡単です。
ですが、こうした職場の知り合いと築いた関係は、多くの人が考えるよりもはるかに、人間の絆やコミュニティーの意識にとって重要なものだといえましょう。
言うまでもないことですが、自分が愛する人たちと過ごすことで孤独は癒やされ、人生の満足度は高まるものです。
ですが、人間の社会性に関する最新の学術調査によって、そこにいくらか複雑さやニュアンスが加わり、単なる知り合いや、あるいは見知らぬ人との交流でも、孤独感が和らぎ、幸福感が高まる可能性があることが分かってきました。
研究結果によると、会話が発生しうる場所は公共交通機関やジム、コーヒーショップなど豊富に存在しています。
職場も間違いなく交流の場の一つだと言えるでしょう。
井戸端会議が職場のパフォーマンスや結束力を高めることは広く知られていることです。
話し相手がいるということは、働く人生を豊かにしてくれるのです。
ハーバード大学のマリオ・スモール教授(社会学)によると、われわれは重要な問題について、感情的に親密な人よりも、むしろ身近に会う人に相談する傾向があるのだそうです。
身近さが単なる知り合いや同僚を頼るべき親友に変えるのです。
日常的に話す相手が人間関係の基盤になるとの考え方は、もしオフィスに二度と戻らなければ、何を失う可能性があるのだということを示唆しています。
筆者はコロナ前の調査で、116人の対象者に最近の社会的交流について1日5回、時間を決めずに5日連続で質問しました。
その結果、近況を語ったり、冗談を飛ばしたり、意味のある会話をしたりする時間を持つことに共通していたのが、相手が誰であるかにかかわらず、人とつながる感覚は幸福感が増すということでした。
意義深いことは、厳密に仕事の話題に限定した場合、そのようなメリットはほとんど生じなかったと言うことです。
仕事の話をした後の幸福感を回答者に尋ねると、一人の時と大して変わらなかったのです。
言い換えると、物理的に近くにいることで、仕事もプライベートも含めた会話の機会が生まれ、さらには友情を育む苗床ともなりうると言うことです。
知り合いとの絆であれ、職場の仲間から発展した友情であれ、こうしたメリットを享受するのに不可欠なのは空間の共有であると言えます。
誰かと共に仕事をすることと、誰かの「近くで」仕事をすることの決定的な違いがそこにあるのです。
もちろん、職場でのコミュニケーションに代わる大量のZoom(ズーム)やSlack(スラック)、メールがあふれてはいますが、これらのツールは対面の会話とは根本的に異なるものです。
以前は廊下で短い会話をしたり、会議の後に三々五々集まって話したりしたことの多くが、今や全く行われないか、スケジュールを組む必要があるかのどちらかになりました。
ビデオチャットやメールは偶発的なものでも、気軽でもなく、自分が明確な意図を持ち、同僚の時間や自主性に配慮しなければなりません。
残念ながら、人は交流を保つことが得意ではありません。
生活を共にしていない相手に、毎日連絡を取ることは極めてまれです。
それは今に始まったことではないのです。
手紙や固定電話の時代も同じでした。
おそらく今後も、変わることはないでしょう。
The Wall Street Journal:2021年3月22日
原題:What We Lose When We Don’t See Our Work Acquaintances
引用:https://www.wsj.com/articles/what-we-lose-when-we-dont-see-our-work-acquaintances-11616079601